

|
|
|
時間 |
ねらい・学習活動 |
関 |
考 |
表 |
知 |
学習活動における具体の評価規準例 |
1 |
いろいろな入れ物に入っている水のかさをデシリットルますではかる活動から小数の学習課題をとらえた上で,はしたのかさを小数で表すことを通して整数,小数の意味を理解する。 |
■ |
【知】「はしたのかさを小数で表し,整数,小数の意味を理解する」 B:1デシリットル未満のかさを小数で表すことができる。 A:上記のことに加え,1デシリットルをこえるかさを小数で表すことができる。 |
|||
2 |
テープの長さをcm単位で表すことを考えることを通して,小数の意味の理解を深め,身のまわりにある小数をさがし出すことができる。 指導案  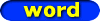 |
■ |
■ |
【知】「はしたの長さや重さを小数で表すことができる」 B:1m何十cmの長さをmで表したり,2kg何百gの重さをkgで表したりできる。 A:上記のことに加え,小数で表された長さやかさを複名数で表すことができる。 【関】「身のまわりで使われている小数を探し出すことができる」 B:身の回りで小数が使われているものを1つは想起してノートにかいたり発表したりすること ができる。 A:身のまわりで小数が使われているものをいくつか想起してノートにかいたり発表したりする ことができる。 |
||
3 |
数直線上の小数をよんだり,数直線上に小数を表したり,小数の大小を比較したりして,小数のしくみをいろいろな見方から理解する。 |
■ |
■ |
【知】「いろいろな見方から小数の仕組みを理解する」 B:0.1を何個集めた数かがわかる。 A:上記のことに加え,1を何個と0.1を何個集めたかがわかる。 【表】「数直線上に小数を表すことができる」 B:数直線上に正しく小数を表すことができる。 A:上記のことに加え,2つの小数の大きさを比べることができる。 |
||
4 |
2つのジュースや牛乳の量の合計や差を考えることを通して,小数のたし算とひき算の意味を理解し,簡単な小数のたし算とひき算ができる。 |
■ |
■ |
【考】「小数のたし算やひき算の仕方を考える」 B:図や数直線で操作しながら,合計や差の結果を0.1のいくつ分か数えることでたし算やひき 算ができることに気付きノートにかいたり発表したりすることがことができる。 A:もとの小数がそれぞれ0.1のいくつ分か考え,その合計や差を求めることでたし算やひき算 ができることに気付き,ノートにかいたり発表したりすることができる。 【表】「簡単な小数のたし算とひき算ができる」 B:16問中,8問以上できる。 A:16問,全問できる。 |
||
5 |
小数が整数と同じしくみで表されていることを用いて,小数の加法や減法の計算の仕方を考えることができるとともに,その筆算ができる。 |
■ |
■ |
【考】「小数のしくみを考えて,小数のたし算・ひき算の筆算の仕方を考えることができる」 B:小数点に注意しながら位をそろえ整数の時と同じように計算すればよいことに気付き,ノー トにかいたり発表したりすることができる。 A:上記のことに加え,計算の結果小数点以下に0がついた場合の0の処理方法を考え,ノート にかいたり発表したりすることができる。 【表】「小数のたし算・ひき算の筆算ができる」 B:16問中,8問以上できる。 A:16問,全問できる。 |
||
6 |
小数の加減演算を判断して問題を解決するとともに,作問を通して小数の加減法の活用ができる。 |
■ |
■ |
【知】「小数の加減演算を判断して,問題を解くことができる」 B:文章の問題が1問以上できる。 A:文章の問題が3問すべてできる。 【関】「作問を通して,小数の加減法の活用ができる」 B:さし絵を見て,たし算やひき算の問題を考え,ノートにかいたり発表したりすることができ る。 A:上記のことについて,さらに内容を加えた問題を考え,ノートにかいたり発表したりするこ とができる。 |
||
7 |
基本的な小数の意味やしくみを理解し,楽しみながら小数の計算練習をすることを通して,小数への興味・関心を深める。 |
■ |
【考】「0.5?,0.2?はいる2つのコップを使って,いろいろな大きさのかさを意欲的に作ることができる」 B:0.7?,0.3?,0.4?など1回の操作で量り取ることができる量の作り方を考え,ノートにかいた り発表したりすることができる。 A:上記のことに加え,0.5-0.2+0.5=0.8など2回以上の操作ではかり取ることができる量の作り 方を考え,ノートにかいたり発表したりすることができる。 |
|||
8 |
練習をすることを通して,小数のしくみについての理解を深める。 |
|||||
9 |
ふく習をすることを通して,これまでの学習内容ついての習熟を図る。 |
平成10年度学習指導要領(旧学習指導要領)に準じています。ご注意ください。
このページから訪問された方へ
香川県算数教育研究会(香算研)は香川県の教員で構成されている算数教育研究の同好会です。
このホームページでは,実践例やプリント・ワークシートの充実を図っています。
ぜひ,TOPページからご覧ください。
![]()